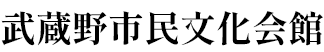アレクサンダー・ガジェヴ&アンドレア・ミアッツォン ピアノ・デュオ
イベントカテゴリ: 音楽(クラシック)

- 開催日
-
2025年11月17日(月曜日)
- 開催時間
-
午後7時開演(午後6時30分開場)
- 開催場所
-
武蔵野市民文化会館 小ホール
交通・アクセス - 対象
-
小学生、中学生・高校生・大学生、大人
- チケット 発売情報
-
8月9日(土曜日) 10時00分発売
予定枚数終了 - 出演
-
アレクサンダー・ガジェヴ
アンドレア・ミアッツォン - チケット
-
全席指定
一般 2,700円 友の会 2,400円 - 主催
- (公財)武蔵野文化生涯学習事業団
プログラム
前半はガジェヴのソロ演奏(ショパン作品)をもとに、ミアッツォンが即興。
後半はお客さまからのリクエストをもとに、2台ピアノ即興!
演奏者とのインタラクティブかつクリエイティブな時間をお楽しみください!
前半 オール・ショパン・プログラム
F.F.ショパン:マズルカ ヘ短調 Op.63-2
F.F.ショパン:《24のプレリュード(前奏曲集)》より 前奏曲 第4番 ホ短調 Op.28-4
F.F.ショパン:ノクターン第4番 ヘ長調 Op.15-1
F.F.ショパン:バラード 第4番 ヘ短調 Op.52
F.F.ショパン:マズルカ(遺作) イ短調 Op.68-2
F.F.ショパン:マズルカ 嬰ヘ短調 Op.6-1
F.F.ショパン:プレリュード 嬰ハ短調 Op.45
F.F.ショパン:《24のプレリュード(前奏曲集)》より 前奏曲 第24番 ニ短調 Op.28-24
アレクサンダー・ガジェヴと遊ぼう!
メータ、ゲルギエフ、テミルカーノフなどの名指揮者と協演!
前回のショパン・コンクールで反田恭平と2位を分け合ったガジェヴが
ドイツから友人の作曲家ミアッツォンを呼んで即興の世界をお送りします。
音楽の魅力を知り尽くした方にお贈りする、武蔵野らしい「裏メニュー」。お楽しみください!
※未就学児はご入場いただけません。
※やむを得ない事情により、内容が変更となる場合があります。ご了承の上、ご予約ください。
※車椅子席は電話及び窓口でのみ販売いたします。ご了承ください。
※発売日はインターネット&電話のみ受付。残券がある場合は、発売日の翌日より窓口でも受付いたします。
※公演実施の場合、チケット購入後のキャンセル・変更は一切いたしかねます。ご了承の上、ご予約をお願いいたします。
アレクサンダー・ガジェヴ プロフィール
2021年10月第18回ショパン国際ピアノ・コンクールで第2位及びクリスチャン・ツィメルマン賞(ソナタ最優秀演奏賞)を受賞。
2021年7月シドニー国際ピアノ・コンクールで優勝。
2018年 モンテカルロのワールド・ピアノ・マスターズで優勝。
2015年 第9回浜松国際ピアノコンクールで優勝および聴衆賞を受賞。
音楽と中央ヨーロッパの文化に囲まれた幼少期はガジェヴの歩みを決定づけた。前者は両親がピアノ教師・音楽家であった環境が大きく、後者は生まれ故郷ゴリツィア(イタリア)に由来する。スロベニアとの国境からほど近く、多様な人々・文化・言語がごく自然に交差している街である。これらは、さまざまな音楽様式や音楽言語を貪欲に吸収し、自身に合わせて変化させる天性の能力をそなえたガジェヴに多大な影響をおよぼしてきた。
父に師事し、9歳の時にオーケストラと初共演、10歳で初リサイタルを開いた。17歳で2013年、イタリアの教育機関で最高評価を得た若手だけが競うコンクール「プレミオ・ヴェネツィア」への出場を許され、その覇者となった。その後現在にいたるまで出場するコンクールでほぼすべて優勝。2019年にはBBCニュー・ジェネレーション・アーティストに選ばれ、23年にはイタリアの権威あるアッビアーティ賞と、スロベニアのプレシェーレン賞を受賞。そして2023/24年からUnione Musicaleのアーティスト・イン・レジデンスを、また「ノヴァ・ゴリツィア/ゴリツィア欧州文化首都2025」の文化大使を務める。
これまでにルイージ指揮/RAI国立響、ゲルギエフ指揮/マリインスキー劇場管、メータ指揮/フィレンツェ五月音楽祭管をはじめ、指揮者ではテミルカーノフ、ヴィット、井上道義、高関健、広上淳一、山田和樹らと共演している。今年6月のウィーン楽友協会でのスロベニア・フィルとの共演も大成功に終わった。2024年からは毎年ロンドンのウィグモアホールでリサイタルを行う。音楽祭への参加も多く、ヴェルビエ音楽祭、オールドバラ音楽祭などに参加している。
アンドレア・ミアッツォン プロフィール
ピアニストとして音楽の道を歩み、マルコ・テッツァに師事してヴィチェンツァ音楽院を卒業。その一方でオペラや交響作品にも没頭し、音楽理論、和声、作曲、即興の理解を深めた。その後、パドヴァ音楽院のジョヴァンニ・ボナートのもとで作曲を学び、さらにベルリンのハンス・アイスラー音楽大学でハンスペーター・キブルツに師事。近年は、音楽理論について包括的なプログラムも修了し、そこから即興演奏の探求をさまざまなスタイルの方向へと広げている。
即興、和声、作曲の教師としての活動に加え、編曲、執筆、劇場のための作曲のほか、オーケストラのためのピアニスト、伴奏者としても活躍している。クラシック、現代音楽からサルサ、声楽ポリフォニー、サーカス、劇場音楽まで、あらゆる形態の音楽に深く魅了され、オープンで好奇心を絶やさぬ精神で音楽に取り組んでいる。